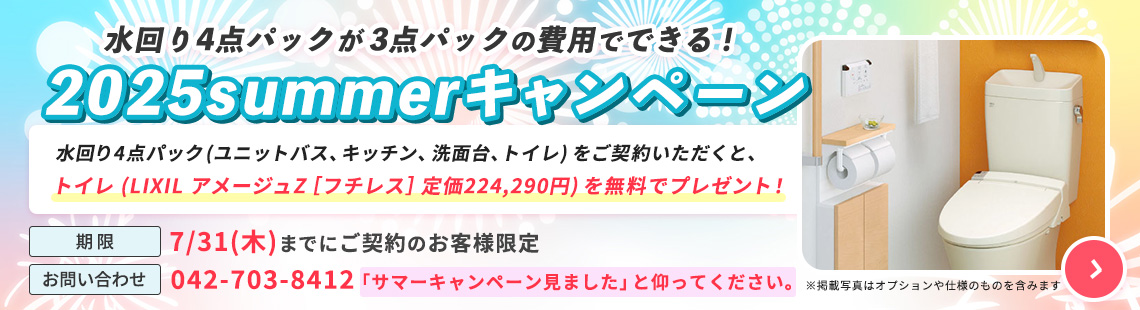2025.09.17
床のきしみと季節の関係|原因・対策・予防法をわかりやすく解説
家の中を歩いていると、床が「ギシギシ」ときしむ音が気になることはありませんか?
特に季節の変わり目になると、「冬は音が大きくなる」「梅雨になるときしみが増える」と感じる方も多いはずです。
この記事では、床のきしみが季節によって変化する理由と、その原因・対策・日常の予防法まで、わかりやすく解説します。
床のきしみを放置してしまうと、住宅の劣化や売却時の価値にも影響します。この記事を通して、正しい知識と対策を身につけておきましょう。
床のきしみが季節によって変わるのはなぜ?

床のきしみは、一年を通して同じように起きるわけではありません。季節の変化によって、音の大きさや頻度が変わる理由があります。
ここでは、その主な原因について詳しく見ていきましょう。
湿度の変化で木材が膨張・収縮するから
床に使われているフローリング材や下地材は、多くが木材です。
木は湿気を吸ったり吐いたりする性質があるため、湿度が高くなると膨張し、低くなると縮みます。
この膨張・収縮によって床材が擦れ合い、「ギシギシ」とした音が発生します。
特に湿度の変化が大きい梅雨や冬にきしみが目立ちやすくなります。
気温の変化で床材と構造材の間にすき間ができるから
気温が下がると木材は収縮し、上に貼られているフローリングと下地材との間にすき間ができます。
このすき間に力が加わると、木材同士が擦れて音が出ることがあります。
特に朝晩の寒暖差が大きい季節には、きしみ音が増える傾向があります。
また、新築直後の家では木材がまだ安定しておらず、温度変化の影響を受けやすいです。
暖房や冷房の使用で室内環境が変わるから
エアコンや暖房器具を使うことで、部屋の温度や湿度が大きく変化します。
冬は暖房で乾燥しやすく、夏は冷房で湿度が下がることで、木材が急激に縮む・膨張するケースもあります。
このような人工的な環境変化も、床のきしみに影響します。
機器を使う際は、湿度にも注意を払うことが重要です。
床のきしみと季節の関係をくわしく解説
ここでは、季節ごとに起こりやすい床のきしみの特徴と、その理由についてより具体的に説明していきます。
冬場は乾燥で木材が縮みやすい
冬は空気が乾燥し、室内の湿度も下がります。
木材は水分を失うことで収縮し、結果としてフローリング同士がすれて音が出やすくなります。
特に暖房を使っている部屋では、乾燥が進んで木の収縮が大きくなりがちです。
このような場合には、加湿器を使って湿度を50〜60%程度に保つことが効果的です。
夏場は湿気で木材が膨張しやすい
夏は湿度が高く、木が水分を吸って膨らみます。
この膨張によって、フローリングがきつくなりすぎて持ち上がったり、すれたりすることがあります。
床が盛り上がってしまうと、踏んだときに大きな音が出ることもあります。
除湿機やエアコンの除湿機能で湿度をコントロールすることが大切です。
梅雨時は湿度が高く、床材の動きが大きくなる
梅雨は特に湿度が高く、木材が一番膨張する時期です。
この時期に床のきしみが強くなるのは、木材が限界まで水分を吸って膨張しているからです。
その結果、床板同士が強く押し合い、きしみ音や歪みが発生しやすくなります。
この時期の湿度管理は、住宅の健康にとっても非常に重要です。
季節ごとに家全体の気温・湿度のバランスが変わる
建物は気温や湿度の変化に影響されるため、季節によって家の構造自体が微妙に動いています。
床だけでなく、壁や天井も同様に変化しており、それが床のきしみにも影響を及ぼしています。
このような家全体のバランスの変化が、床の異音につながることもあります。
だからこそ、季節ごとのケアが必要なのです。
床のきしみが季節でひどくなる主な原因とは?

では、なぜ季節によってきしみがひどくなる家とそうでない家があるのでしょうか?
ここでは、きしみが悪化する原因をいくつか紹介します。
築年数が経過して木材が劣化しているから
築年数が長くなると、木材が乾燥や湿気にさらされ続け、徐々に劣化していきます。
劣化した木材は柔軟性を失い、きしみやすくなるのです。
さらに、繰り返しの膨張・収縮で固定が緩くなっている可能性もあります。
築10年以上経っている場合は、定期的な点検をおすすめします。
断熱・気密性能が低く外気の影響を受けやすいから
古い住宅や断熱性能が低い家は、外気温や湿度の影響を受けやすくなります。
その結果、室内の湿度や温度が安定せず、木材の動きが大きくなります。
リフォームによる断熱材の強化や窓の気密性向上が有効です。
快適な室内環境づくりが、床のきしみ予防にもつながります。
フローリング材と下地材の固定がゆるくなっているから
床はフローリング材の下に「根太(ねだ)」や「下地材」と呼ばれる木材があり、そこにしっかりと固定されています。
この固定がゆるくなると、歩くたびにフローリングが動いて音が出ます。
特に経年劣化によって釘や接着剤が効かなくなることが原因です。
このような場合は、床下補修や再固定工事が必要です。
湿度管理が不十分で木材の動きが大きくなるから
室内の湿度を年間を通して適切に保つことができていないと、木材の動きが極端になります。
たとえば、冬に湿度30%以下、夏に70%以上になるような家では、木材の変化が非常に激しくなります。
こうした極端な変化が、きしみの原因となるのです。
湿度は見えないため、湿度計で定期的に確認しましょう。
季節による床のきしみを放っておくとどうなる?
「音がするだけだから大丈夫」と思って放置していると、実は大きな問題に発展することもあります。
床のきしみは家の異常のサインかもしれません。以下に放置によるリスクを紹介します。
騒音ストレスが日常的に発生する
毎日の生活の中で、歩くたびに「ギシギシ」と音がするのは、精神的にも負担になります。
静かな夜や早朝など、音が目立つ時間帯では特にストレスになります。
家族やペットが音に敏感な場合は、生活の質が下がる原因になります。
安心して暮らすためにも、早めの対策が必要です。
構造部分のゆるみが進行する可能性がある
床のきしみは、構造部材がしっかり固定されていない状態を示すことがあります。
放っておくと、そのゆるみが進行し、床がたわんだり、沈んだりすることもあります。
最悪の場合は、安全性にかかわる大きな修繕が必要になることもあります。
音が出始めたら、早めにチェックを行いましょう。
シロアリやカビの発生リスクが高まる
湿気が多い状態で床のきしみが続いている場合、木材が水分を含みすぎている可能性があります。
このような環境では、シロアリやカビが発生しやすく、家の構造に深刻な被害を与えることもあります。
見た目ではわからない被害が進行することもあるため、注意が必要です。
定期的な床下点検が大切です。
売却時の住宅価値が下がるおそれがある
家を売却する際、買主は内覧で床の状態をチェックします。
床がきしんでいると、「メンテナンスされていない家」という印象を与え、住宅価値が下がる原因になります。
不動産の査定でもマイナスポイントになることが多いです。
資産価値を保つためにも、こまめなメンテナンスが必要です。
季節ごとの床のきしみ対策のポイント

床のきしみを抑えるには、季節ごとの環境変化に合わせた対策が有効です。
ここでは、四季ごとの対処法を紹介します。
冬は加湿器で湿度を保つ
冬は乾燥により木材が縮みやすく、きしみが増えがちです。
湿度が40%以下になると、木材が大きく収縮することがあります。
加湿器を使って湿度を50〜60%に保つことで、木材の変形を防ぐことができます。
加湿しすぎると結露の原因になるので、湿度計でこまめに確認しましょう。
夏は除湿器やエアコンで湿度を下げる
夏は湿気が多く、木が膨張して床材が押し合い、きしみが起きやすくなります。
この対策には、除湿器やエアコンのドライ機能を活用しましょう。
特に風通しの悪い部屋や北向きの部屋は湿気がたまりやすいため、重点的に除湿が必要です。
クローゼットや収納の中も一緒に除湿すると、カビ対策にもなります。
梅雨時は除湿と換気をしっかり行う
梅雨は最も湿気が多い時期です。
床のきしみだけでなく、カビやダニの発生にもつながります。
除湿器やエアコンに加えて、窓を開けての換気もこまめに行いましょう。
浴室やキッチンなど、水回りから湿気が広がることもあるため、換気扇も有効活用してください。
秋は床下の点検をして冬に備える
秋は気温も湿度も安定しているため、点検や修理に最適な時期です。
冬に備えて床下のチェックを行い、ゆるみや湿気がないか確認しましょう。
また、ワックスがけやネジの締め直しなど、セルフメンテナンスも行いやすい季節です。
本格的な寒さが来る前に準備しておくことが、きしみ予防につながります。
床のきしみを季節に関係なくおさえる方法
一時的な対策だけでなく、根本的にきしみを解消する方法もあります。
床の構造や材質にアプローチすることで、季節を問わず快適な住まいが実現できます。
床下の補強工事を行う
床の構造部分が弱くなっている場合は、床下からの補強が有効です。
たとえば、「根太」や「大引き」といった下地材を追加することで、床の安定性が増します。
専門業者に依頼すれば、家の状態に合わせた補強プランを提案してくれます。
築年数が経っている家ほど、検討する価値があります。
フローリングの再固定や張り替えをする
フローリングの浮きやすき間が原因であれば、再固定や張り替えで解消できます。
部分的な補修でも効果がある場合も多く、費用を抑えて対策が可能です。
広範囲にわたる場合は、全面リフォームも検討しましょう。
仕上げの際は、防音性や耐湿性を考慮した材料を選ぶのがおすすめです。
防音・防湿マットを使って床材の動きを軽減する
手軽な方法として、防音・防湿マットをフローリングの上に敷くという選択肢もあります。
これにより、床材の動きやすき間の摩擦を軽減でき、きしみ音が小さくなります。
特にマンションや2階の床に使うと、下階への騒音も防げます。
ホームセンターや通販で手軽に購入でき、DIYにも向いています。
専門業者に床診断を依頼する
原因が特定できない、複数の要因が考えられる場合は、専門業者の床診断を受けましょう。
調査では、床下の構造、湿度、断熱状況などを総合的にチェックしてくれます。
専門家のアドバイスをもとに対策を講じれば、長く安心して暮らすことができます。
費用はかかりますが、それ以上の価値がある場合も多いです。
季節の変わり目に多い床のきしみを防ぐ日常の工夫
大がかりな工事をしなくても、日常生活の中でできる予防法があります。
簡単な工夫を習慣にすることで、きしみの発生を抑えることができます。
毎日の換気で湿度をコントロールする
換気は湿度を安定させるために非常に重要です。
湿気がたまると木材が膨らみやすくなり、乾燥しすぎると縮みます。
1日2回程度、窓を10分ずつ開けるだけでも効果があります。
換気扇やサーキュレーターを併用するとさらに効率的です。
家具の重みで床に負荷をかけすぎないようにする
重たい家具が床の一部分に長期間置かれていると、床材や下地にゆがみが生じやすくなります。
家具の位置を時々変える、脚の下にクッション材を置くなどの工夫をしましょう。
重みの偏りをなくすことで、床のきしみを防ぐことができます。
また、定期的に家具の下も掃除することが湿気対策にもなります。
フローリングワックスで床材の乾燥を防ぐ
木製の床は、表面が乾燥してくるときしみやすくなります。
フローリング専用のワックスを使うことで、保湿と滑り止めの効果が期待できます。
年に1〜2回のワックスがけを習慣にすると良い状態が保てます。
天然成分のワックスであれば、小さなお子さんやペットにも安心です。
定期的に床下点検をして早期発見する
床の構造や湿気の状態は、日常生活ではなかなか見えません。
専門業者に年1回程度の床下点検を依頼すると、異常を早期に発見できます。
特に築10年以上の住宅では、点検が大きなトラブルを防ぐカギとなります。
定期的なチェックが、家を長持ちさせる秘訣です。
まとめ|床のきしみと季節の関係・原因・対策をしっかり理解しよう

床のきしみは、湿度や温度の変化によって起こる自然な現象ですが、放っておくと住宅の寿命や住み心地に影響を与えます。
季節ごとに適切な対策をとり、日常のちょっとした工夫を積み重ねることが大切です。
この記事を参考に、ご自宅の床の状態を見直して、快適な暮らしを守っていきましょう。
早めの対策が、将来の大きな出費を防ぐことにもつながります。
フローリングや床をリフォームするならグランディル
今回この記事では、床のきしみと季節の関係についてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけに水回りをまとめてリフォームすることを検討している方がいらっしゃるかと思います。
フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。
グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。
大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。
また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。
大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。
ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。