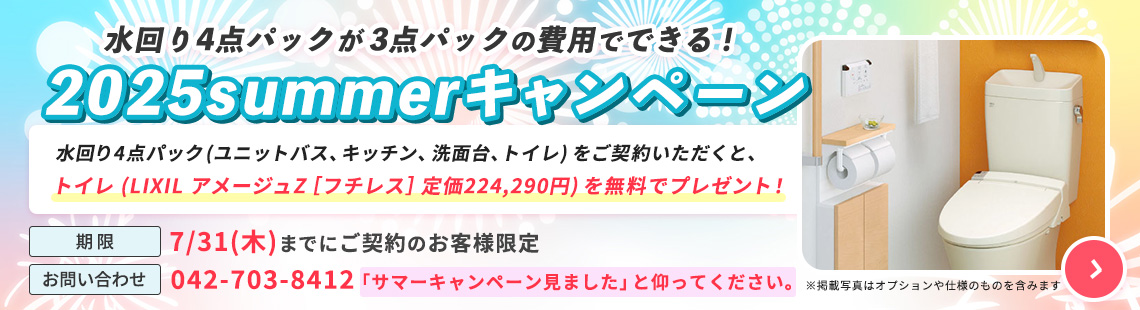2025.10.21
床鳴り(ギシギシ音)の原因と対策を徹底解説!放置せずに快適な住まいを守ろう
家の床から「ギシギシ」「ミシミシ」と音が鳴ることはありませんか?
それは「床鳴り」と呼ばれる現象で、放置すると住宅の劣化や安全性の問題につながることがあります。
この記事では、床鳴りの原因から、セルフチェック方法、簡単な対策、そして業者に頼むべきケースまで、わかりやすく解説します。
原因を知って正しい対応をすれば、大切な住まいを長く快適に保てます。ぜひ最後までお読みください。
床鳴り(ギシギシ音)が起こる原因とは?

床鳴りの主な原因は、床材や下地、湿気など複数の要素が関係しています。以下では主な理由を順に説明します。
床材のゆるみが原因
最もよくある原因の一つは、フローリングや合板などの床材が浮いたり、固定が甘くなっている状態です。
長年使用していると、釘やビスがゆるんだり、接着剤がはがれて隙間ができることがあります。
このような床材のわずかなズレが、人が歩いたときに摩擦や反発を起こし、「ギシギシ」という音が発生します。
特に集合住宅や築年数の古い戸建てで多く見られます。
下地の木材が摩耗している
床材の下には「根太(ねだ)」や「大引き(おおびき)」と呼ばれる木材の骨組みがあります。
これらが劣化していたり、木材同士がこすれ合っていると、音が鳴る原因になります。
また、木材の乾燥や老朽化によって強度が落ち、きしむ音が出やすくなります。
根太と床材がしっかり固定されていないと、小さな力でも音が鳴ってしまうことがあるのです。
湿気や乾燥で木が伸び縮みする
木材は湿気を吸うと膨らみ、乾燥すると縮みます。これを「木の呼吸」と呼びます。
季節によって室内の湿度が変わることで、床材がわずかに動き、ギシギシという音が生じるのです。
特に梅雨や冬場の乾燥期に床鳴りがひどくなる場合は、湿度の影響が疑われます。
住宅の気密性や換気環境も関係しており、床下の湿気管理がとても重要です。
施工不良で隙間ができている
新築やリフォーム直後に床鳴りがする場合、施工不良が原因の可能性があります。
たとえば、床材の貼り付けが不十分だったり、下地の間隔が広すぎると、歩いた際にたわみが起きて音が鳴ります。
プロの業者でもまれに施工精度が甘いことがあるため、新築でも安心できないのが現実です。
施工不良による床鳴りは、自分で直すのが難しいため、専門業者に相談しましょう。
床鳴り(ギシギシ音)が放置されるとどうなる?
床鳴りをそのままにしておくと、音だけでなく、家全体に悪い影響を与えることがあります。
音がどんどん大きくなる
最初は気にならなかった音も、時間が経つと悪化することが多いです。
原因となるゆるみやズレが広がって、歩くたびに「ギィー」「ミシッ」という大きな音が鳴るようになります。
特に集合住宅では、下の階への騒音トラブルにつながる恐れもあるため、注意が必要です。
気づいた時点で早めに対処することが大切です。
床が抜けるリスクがある
床鳴りが進行すると、床材の強度が落ちてしまうことがあります。
特に下地が腐っていたり、シロアリに食われている場合は、最悪の場合、床が抜ける危険性もあります。
小さな異音を軽視せず、住宅の安全性を守る意識を持つことが大切です。
特に高齢者や子どもがいる家庭では、安全面からも放置はおすすめできません。
家の劣化が進むサインになる
床鳴りは、家のどこかが劣化しているサインの一つです。
床下の湿気が原因なら、同時にカビや腐食が進行している可能性もあります。
また、建物全体のゆがみや傾きが原因で床鳴りが出るケースもあります。
床鳴りを通じて、家の状態を見直す良いタイミングにもなります。
床鳴り(ギシギシ音)のチェックポイントを確認しよう

まずは自分の家のどこで、どのように音が鳴っているのかをチェックしましょう。
鳴っている場所を特定する
まずは、どの部屋・どの位置で音が鳴っているのかを確認します。
静かな時間にゆっくり歩いてみて、「ギシギシ」と鳴る位置をマスキングテープなどで印をつけると便利です。
複数の箇所で音がする場合は、それぞれの原因が異なる場合もあります。
位置を正確に把握することで、修理や対策がスムーズになります。
床材の浮きや隙間を確認する
音がする場所をよく見て、床材が浮いていたり、隙間ができていないかチェックします。
目で見てわかりにくい場合は、軽く押してみて沈み込むかを確認しましょう。
反発感がある場合、床材が下地に密着していない可能性があります。
このチェックで、床材のゆるみか構造的な問題かを見分ける手がかりになります。
床下に湿気やカビがないか見る
床下点検口があれば、懐中電灯で内部を照らして湿気やカビ、異臭がないかを確認します。
木材が黒ずんでいたり、白っぽいカビが生えている場合は湿気対策が必要です。
床鳴りと同時にカビやシロアリのリスクも抱えていることがあります。
異常を見つけたら、専門のシロアリ業者や住宅点検業者に依頼しましょう。
床鳴り(ギシギシ音)の簡単な対策方法3選
床鳴りの原因が軽度であれば、自分でできる対策で音を軽減できることもあります。
ここでは特に効果が高いとされる簡単な方法を3つ紹介します。
市販の床鳴り防止剤を使う
ホームセンターなどで手に入る「床鳴り防止スプレー」や「すき間補修剤」を使う方法です。
フローリングの隙間にスプレーを吹き込むと、摩擦が軽減されて音も抑えられます。
ただし、これはあくまで一時的な対策であり、根本的な修理ではありません。
手軽にできる対策としては有効ですが、繰り返し使っても改善しない場合は他の方法を検討しましょう。
床に滑り止めシートを敷く
家具の下や、よく歩く場所に「滑り止めシート」を敷くことで、床材のズレやたわみを抑えることができます。
滑り止め効果だけでなく、振動や衝撃を和らげて音を軽減する効果もあります。
特にテーブルや椅子など、動く家具の下に敷くのが効果的です。
工具不要で誰でもできるので、床鳴り対策の入門としておすすめです。
ジョイントマットで圧力を分散する
プレイマットやジョイントマットを床に敷くことで、歩いたときの圧力が分散され、床材への負荷が軽減されます。
厚手のマットほど効果が高く、防音対策にもつながります。
床に傷がつきにくくなるため、ペットや子どもがいる家庭にもぴったりです。
「音が気になるけど大きな修理はしたくない」という人に最適な方法です。
床鳴り(ギシギシ音)を自分で直すときの注意点

床鳴りをDIYで修理する場合、逆に悪化させてしまうこともあるので注意が必要です。
床下の構造を理解してから作業する
フローリングの下には下地や断熱材など複雑な構造があります。
構造を知らずに釘を打ったり接着剤を流すと、配線や断熱材を傷つけてしまう危険があります。
ネットや書籍で構造を学んだ上で、無理のない範囲で作業しましょう。
不安がある場合は、最初から専門業者に依頼する方が安心です。
間違った修理で悪化する可能性がある
隙間に木材を押し込んだり、強力な接着剤を使ってしまうと、床が反り返ってしまうこともあります。
修理が失敗すると、音が大きくなったり、床材が浮いてしまうなど、状態が悪化することも。
市販の補修キットを使う場合も、必ず使用方法を確認してください。
安易な修理は避け、慎重に対処することが大切です。
マンションでは管理規約を確認する
分譲マンションや賃貸物件では、勝手に修理をするとトラブルになる可能性があります。
マンションには「管理規約」や「使用細則」があり、床材の変更や修理に制限が設けられている場合もあります。
工事をする前に、必ず管理会社やオーナーに相談して許可を取りましょう。
共有部分にあたる可能性があるため、自己判断での作業は禁物です。
床鳴り(ギシギシ音)を業者に依頼すべきケースとは?
自分でできる対策で改善しない場合や、構造的な問題が疑われる場合は、専門業者に相談しましょう。
何度直しても音が止まらないとき
市販の補修剤やマットを使っても効果がない場合は、根本原因が床下にある可能性があります。
繰り返し同じ場所が鳴る場合は、木材の劣化やゆがみが進行しているサインかもしれません。
プロの点検を受けることで、見えない部分の異常も発見できます。
早めの対応が、費用を抑えるカギになります。
床下にカビや白アリの疑いがあるとき
床下の湿気や異臭、黒ずみがある場合は、カビや白アリの被害が疑われます。
この場合、床鳴りだけでなく、住宅の構造そのものが危険にさらされている可能性があります。
白アリは見えないところで木を食べるため、被害が広がりやすいです。
早急に専門業者に相談し、調査・対策を行いましょう。
築年数が古く全体的に傷んでいるとき
築20年以上経過した住宅では、床下の劣化が進んでいることがあります。
床鳴り以外にも、ドアの閉まりが悪い、壁にひびがあるなどの症状が出ている場合は、全体的なリフォームを検討するタイミングです。
部分補修では解決しきれない場合も多く、専門のリフォーム業者に総点検を依頼しましょう。
長期的に住むなら、一度しっかりメンテナンスすることが大切です。
フローリング全体の張り替えが必要なとき
床材が広範囲にわたって浮いている、反っている場合は、張り替えが必要です。
全面張り替えはコストがかかりますが、床鳴りを根本から解消できる最も確実な方法です。
最近では防音性や耐久性に優れた床材も多く、快適さが格段に向上します。
信頼できる業者に見積もりを依頼して、比較検討してみましょう。
床鳴り(ギシギシ音)の予防方法とは?
床鳴りを未然に防ぐためには、日頃からのメンテナンスが欠かせません。
定期的に床下の湿度をチェックする
湿気は床鳴りだけでなく、カビや腐食の原因にもなります。
床下に湿度計を設置したり、換気扇を回して通気をよくすることで、木材の状態を保てます。
特に梅雨時期や冬場の結露が起こる季節は、注意してチェックしましょう。
除湿剤の設置も効果的です。
家具の配置で圧力を分散させる
同じ場所に重い家具を長期間置いておくと、床がたわみ、鳴りやすくなります。
家具の位置を定期的に変えたり、脚にフェルトを貼ることで負担を減らせます。
ピアノや本棚など、重量のある家具は特に注意しましょう。
床への優しさを意識した配置が重要です。
ワックスや保護剤で床材を守る
定期的に床にワックスをかけることで、床材の保護と滑り防止に役立ちます。
保護剤には、木の乾燥やひび割れを防ぐ成分が含まれているものもあります。
きれいに保つことが、結果的に床鳴りの予防にもつながります。
無垢材フローリングの場合は、専用のオイルや保護剤を使用しましょう。
床鳴り(ギシギシ音)に関するよくある質問
ここでは、床鳴りのギシギシ音についてよくある質問をご紹介いたします。
床鳴りは放っておいても大丈夫?
小さな音であれば問題ないこともありますが、徐々に悪化する可能性があるため早めの対処が望ましいです。
特に湿気や木材の劣化が関係している場合は、放置すると修理費用が高くつくことも。
床鳴り防止マットは本当に効果ある?
一定の効果はあります。音が小さくなったり、家具の振動が減ることで床材への負担を軽減できます。
ただし根本原因が深刻な場合には、マットでは改善しません。
マンションの床鳴りは誰が修理する?
専有部分(室内)の問題であれば、原則として居住者の負担となります。
ただし構造や共有部分に原因がある場合は、管理組合や大家の負担になることもあります。
修理前に必ず管理会社へ相談しましょう。
床鳴りの修理費用はいくらぐらい?
小規模な補修なら5,000円〜1万円程度で済むこともあります。
フローリングの全面張り替えや下地補強が必要な場合は10万円〜30万円かかることもあります。
見積もりを数社から取り、費用と工事内容を比較することが重要です。
床鳴りはフローリングだけに起きるの?
主にフローリングで起こりますが、畳やクッションフロアでも床下の構造に問題があれば鳴ることがあります。
床材に関係なく、下地や湿気の状態によって発生することがあります。
まとめ:床鳴り(ギシギシ音)の原因と対策を知って快適な生活を!

床鳴りやギシギシ音は、単なる不快な音にとどまらず、住宅の不調や劣化のサインであることが多いです。
まずは原因を見極め、軽度なら自分で対策し、難しい場合は専門業者に相談するのが安全です。
放置せず、早めに対応することで、安心で快適な住まいを長く保てます。
日頃のメンテナンスや湿度管理を意識しながら、床と上手に付き合っていきましょう。
フローリングや床をリフォームするならグランディル
今回この記事では、床鳴りのギシギシ音の原因や対策についてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけに水回りをまとめてリフォームすることを検討している方がいらっしゃるかと思います。
フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。
グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。
大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。
また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。
大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。
ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。