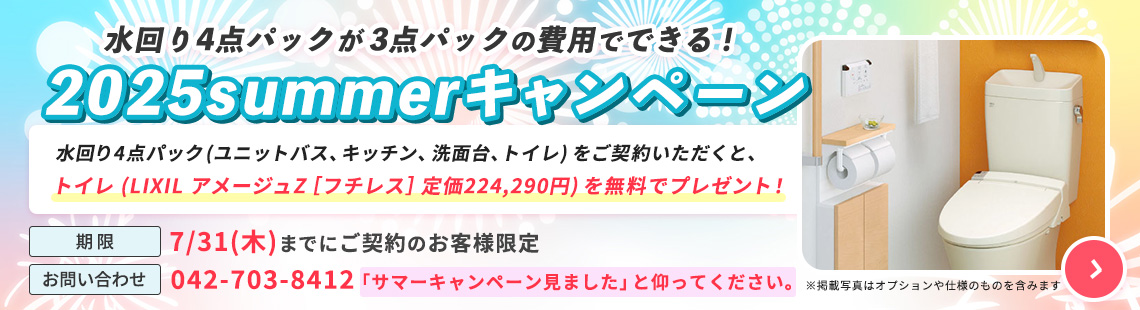2025.08.26
二階の床がきしむ原因と修理方法|放置は危険?費用の目安やDIYの注意点も解説
家の中で「ギシギシ…」と床が鳴る音がすると、不安になりますよね。特に二階の床がきしむと、下の階にまで響くことがあり、生活への影響も大きくなります。
この記事では、二階の床がきしむ原因から対処法、修理費用の目安、DIYの注意点までわかりやすく解説します。
床のきしみを放置すると、家の構造にまで悪影響を与える恐れがあるため、早めの対処が重要です。
なぜ二階の床がきしむのか?考えられる原因とは

二階の床がきしむ音には、さまざまな原因が考えられます。ここでは主な原因を紹介します。
床板の固定が甘くなっている
最も多い原因のひとつが、床板と下地の接合部分のゆるみです。
もともとしっかり固定されていても、年数の経過や人の歩行による振動で、少しずつネジや釘が緩んでくることがあります。
特に木材は湿度や温度の変化により伸び縮みするため、それが原因で固定が甘くなることもあります。
この場合、床を踏んだときにギシッと音がするだけでなく、沈み込みを感じることもあります。
床下の木材が乾燥・劣化している
住宅に使われている木材は、時間が経つと乾燥して収縮します。
木材が乾燥して隙間ができると、部材同士がこすれ合い、きしみ音が発生します。
また、湿気が多い環境では木材が腐ったり、虫害に遭ったりして劣化することも。
これらの劣化が進行すると、きしみ音だけでなく、構造上の強度低下も招きます。
根太や大引きなどの構造材が歪んでいる
床を支える「根太(ねだ)」や「大引き(おおびき)」などの構造材が歪むと、床全体が不安定になります。
構造材の歪みは見た目では分かりにくいですが、音や感触として現れることがあります。
重い家具を長期間置いていたり、水漏れがあったりすると、部分的に変形してしまうこともあります。
このような場合、補強工事が必要になることもあります。
築年数の経過による経年劣化
家が古くなってくると、材料そのものが劣化してきしみやすくなります。
築20年を過ぎたあたりから、床のきしみに関する相談が増える傾向があります。
年月を重ねると、床下の湿気や木材の変化などが積み重なり、小さなゆがみや隙間が発生します。
こうした経年劣化は避けられない部分もあるため、定期的なメンテナンスが大切です。
生活音や振動の影響が積み重なっている
普段の生活での歩行や物の移動など、細かい振動が床に伝わり、少しずつ部材のずれが生じることがあります。
集合住宅や二世帯住宅では、こうした音がトラブルの原因にもなります。
子どもが飛び跳ねたり、ペットが走り回ったりすることでも床に負荷がかかります。
こうした日々の積み重ねが、きしみの原因になることもあるのです。
二階の床がきしむ音を放置するとどうなる?危険な症状に要注意
床のきしみは単なる音の問題ではなく、放置することでさまざまなトラブルにつながる可能性があります。
床がたわんで転倒の原因になる
きしみがある場所は、床材や下地材が劣化している可能性が高いです。
そのまま使い続けると床がたわみ、最悪の場合は抜け落ちてしまうことも。
高齢者や子どもが転倒してケガをするリスクもあります。
「なんとなく気になる」で済ませず、早めに原因を突き止めましょう。
下の階への騒音トラブルにつながる
二階の床がギシギシ鳴ると、下の階に音が響くため、家族間や隣人とのトラブルになることもあります。
特に集合住宅や二世帯住宅では、生活音に敏感な方も多いです。
ちょっとした音でも「うるさい」と感じる人もいるため、早めに対応することが大切です。
騒音対策のためにも、床のきしみは無視できない問題です。
構造部分が腐食し家全体に影響が出る
きしみの裏に、構造材の腐食や破損が隠れている場合もあります。
構造部分の劣化が進むと、家全体の安全性にも影響を与えることになりかねません。
最悪の場合、地震などの災害時に倒壊リスクが高くなることも。
床のきしみを見逃さず、構造チェックのきっかけにしましょう。
シロアリ被害が進行してしまうことがある
木材の腐食や劣化の原因が、シロアリだったというケースもあります。
シロアリは見えないところで静かに被害を広げるため、気づいたときには手遅れということも。
床がきしむ場所の近くに水まわりがある場合は特に注意が必要です。
専門業者に調査を依頼して、早めに対処することが重要です。
二階の床がきしむ場合に確認すべきポイント

床のきしみが気になったら、まず自分で確認できるポイントをチェックしてみましょう。
きしみが出る場所と時間帯を確認する
まずは、きしみ音がする場所を特定しましょう。
どこで、どのようなタイミングできしむのかをメモしておくと、後の修理にも役立ちます。
朝晩の温度差や湿度の違いで音が出る場合もあるため、時間帯も意識してチェックしましょう。
人が歩いたときだけでなく、何もしていないのに音がする場合は要注意です。
床を踏んだときの沈み込みをチェックする
床をゆっくり踏んでみて、沈み込む感覚がないか確かめてください。
沈み込みがある場合は、床下の下地材が弱っている可能性が高いです。
音がしなくても沈み込みだけがある場合もあります。
大きな沈み込みがある場合は、早めに専門業者に相談しましょう。
床下収納や天井裏から木材の状態を調べる
床下収納がある場合は、その中から床下をのぞいてみましょう。
カビ、湿気、シロアリの痕跡などがないかもチェックポイントです。
天井裏から構造材を見られる場合も、可能な範囲で確認してみましょう。
手が届かない部分は、点検カメラなどを使って確認する方法もあります。
近くに水回りがあるか確認する
床のきしみが発生している場所が、トイレやお風呂、洗面所の近くでないかも確認しましょう。
水回り付近は湿気が多く、木材が腐食しやすいため、特に注意が必要です。
水漏れや配管トラブルが原因で床下に影響を及ぼしていることもあります。
気になる場合は、早めに業者に水回りの点検を依頼しましょう。
二階の床がきしむ原因別の修理方法とは?
きしみの原因がわかったら、それに応じた修理方法を検討しましょう。原因によって対応の仕方が変わります。
床板のゆるみは再固定・増し締めで対応する
床板がゆるんでいる場合は、ネジや釘を再度しっかりと締め直す「増し締め」で対処できます。
簡単な工具があれば自分でもできる修理方法ですが、下地材にまで緩みがある場合は専門的な補修が必要になります。
音が出る場所にだけピンポイントで処理を行うことで、費用を抑えることも可能です。
ただし、強く打ち込みすぎると床材を傷つけることがあるため、慎重に作業しましょう。
構造材の歪みは補強工事を行う
根太や大引きなどの構造材に歪みがある場合は、補強が必要です。
専用の金具や補強材を使って強度を取り戻す工事が行われます。
部分補強で済む場合もありますが、劣化が広がっている場合は広範囲の工事が必要になることもあります。
専門の業者による診断と提案を受けてから工事内容を決めるのがおすすめです。
下地の隙間には充填材を使用する
床下の木材同士の隙間がきしみの原因の場合は、専用のパテや発泡材などを使って埋める方法があります。
この方法は比較的費用が安く済み、DIYでも対応可能なケースがあります。
ただし、下地の状態や構造により適した材料が異なるため、専門家に相談したうえで行うのが安心です。
応急処置として使うこともありますが、根本的な解決には至らないこともあるため注意しましょう。
シロアリ被害の場合は駆除と防蟻処理をする
シロアリによって木材が食われている場合は、すぐに駆除と修理を行う必要があります。
被害が広がっている場合は、床だけでなく建物全体の調査・処置が必要になるケースもあります。
また、再発防止のために薬剤処理や定期点検を受けると安心です。
シロアリ対策は専門的な知識と技術が求められるため、必ず専門業者に依頼しましょう。
二階の床がきしむときの修理費用の目安を解説

床のきしみを直すための費用は、原因や修理範囲によって大きく異なります。以下は一般的な費用相場の目安です。
簡易的な補修は1~5万円程度
床板の増し締めやパテ埋めなど、軽微な修理で済む場合は、比較的安価に対応できます。
DIYで対応できる場合は1万円未満に抑えることも可能ですが、安全面を考えると専門業者に依頼するほうが確実です。
部材や道具を買い揃える手間を考えると、専門業者のほうがコストパフォーマンスが高いこともあります。
ただし、きしみが再発しやすいため、応急処置と考えておくとよいでしょう。
根太・大引きの補強は10~30万円程度
床の下地材や構造材に問題がある場合は、補強や部分交換が必要になります。
作業範囲や床の面積によって費用が変動しますが、10~30万円が目安です。
一部だけの補強で済めば10万円前後、広い範囲に及ぶとそれ以上になることもあります。
床下の状況によっては、追加工事やシロアリ対策費用がかかるケースもあります。
床全体の張り替えは30~80万円程度
床材が古く、全面的な張り替えが必要な場合は大掛かりな工事になります。
材料費・施工費を含めて30万円~80万円程度かかるのが一般的です。
使用する床材(フローリング、クッションフロア、畳など)によって価格に差が出ます。
断熱材や防音材の追加など、希望する性能によっても費用は変わってきます。
シロアリ駆除・補修は10~50万円程度
シロアリ駆除の費用は、被害の大きさや作業範囲によって異なります。
駆除だけでなく、木材の交換・補修、防蟻処理を含めると、10万円から50万円以上かかることもあります。
予防のための定期点検や薬剤処理を継続的に行うことも検討しましょう。
駆除費用は一見高く感じるかもしれませんが、放置した場合の修繕費用と比べると、むしろ経済的です。
二階の床がきしむ問題は自分で直せる?DIYの注意点
簡単な補修はDIYでも対応可能ですが、床下構造に関わるような作業は慎重に判断しましょう。
床板のネジ締め程度なら可能
表面の床板がきしむだけなら、ネジやビスで締め直すだけで改善することがあります。
電動ドライバーとネジがあれば、自分でも比較的簡単に対応可能です。
ただし、打ち込む位置や長さを間違えると、逆に床を痛めてしまうことがあるため、事前に構造を確認することが大切です。
施工後もきしみが完全になくならない場合は、無理せず専門業者に相談しましょう。
構造部分に手を加えるのは避ける
根太や大引き、柱などの構造材に関わる作業は、DIYでは行わないほうが安全です。
間違った補修によって、床がさらに弱くなるリスクがあります。
また、建築基準法に関わる構造部分を誤って改造してしまうと、後々のリフォームや売却時にも問題になることがあります。
専門的な知識や技術が必要な部分は、必ず業者に依頼しましょう。
誤った施工で悪化するリスクがある
自己流での修理が原因で、音がひどくなったり、床が浮いてしまったりするケースもあります。
一度失敗すると、やり直しに余計な費用がかかることもあるため注意が必要です。
見えない部分まで影響が及ぶこともあるため、DIYは「できる範囲」で留めましょう。
少しでも不安がある場合は、無理をせずプロに相談するのがベストです。
専門業者に相談するのが安全
床のきしみは、構造的な問題が隠れていることがあるため、自己判断には限界があります。
早めに専門業者に見てもらうことで、適切な処置ができ、将来的なトラブルも防げます。
無料の現地調査や見積もりを行っている業者も多いため、気軽に相談してみましょう。
複数の業者から見積もりを取ることで、費用の相場も把握しやすくなります。
二階の床がきしむ音を防ぐための日常的な対策

床のきしみを未然に防ぐためには、日頃のちょっとした工夫やメンテナンスが効果的です。
定期的に床を掃除して湿気をためない
ホコリやゴミが溜まると、床下の湿気がこもりやすくなります。
定期的な掃除で風通しをよくし、床材の劣化を防ぎましょう。
特に家具の裏側や角の部分は湿気が溜まりやすいため、こまめな掃除が大切です。
カビやダニの発生も防げるため、健康面でもメリットがあります。
家具の配置を変えて負荷を分散する
重い家具が同じ場所にずっと置かれていると、床材に偏った負荷がかかります。
ときどき家具の配置を変えることで、床材の歪みを防ぐことができます。
特にタンスや本棚など重量のある家具の下には、床保護パッドを敷くのもおすすめです。
負荷を分散させることで、構造材へのダメージも軽減されます。
除湿機や換気で床下の湿度を管理する
床下の湿度が高くなると、木材の劣化やシロアリ被害の原因になります。
湿度の高い時期は除湿機や換気扇を使って、湿気対策を行いましょう。
通気口のまわりに物を置かないようにするのもポイントです。
換気扇付きの床下点検口を設置することで、効率的に湿度をコントロールすることも可能です。
床材にワックスをかけて保護する
フローリングなどの床材は、ワックスがけによって表面の傷や乾燥を防ぐことができます。
半年~1年に一度は、専用の床用ワックスを使用してメンテナンスしましょう。
床の美しさを保つだけでなく、耐久性を高める効果もあります。
ワックスがけの前には、しっかり掃除をしてから行うことが大切です。
まとめ|二階の床がきしむのを放置せず、原因と修理費用を知って安全な住まいへ
二階の床のきしみは、音だけでなく家の安全性にも関わる重要な問題です。放置せず、早めの対処が必要です。
原因を早期に特定して対処することが大切
床のきしみの原因を正しく把握し、適切な方法で修理することが安全な住まいへの第一歩です。
軽度な場合はDIYで対応できることもありますが、構造に関わる場合はプロに任せるのが確実です。
状況に応じた修理方法と費用を知っておくと安心
修理方法によって費用は大きく変わるため、事前に相場を知っておくことで無駄な出費を防げます。
複数の業者に見積もりを取ることで、より納得のいく選択ができるようになります。
DIYでは限界があるため専門業者の相談も視野に入れる
簡単な補修は可能でも、構造部分の修理やシロアリ対策などは専門性が求められます。
無理せず早めに業者へ相談することで、トラブルを未然に防げます。
日常の工夫できしみの予防もできる
定期的な掃除や家具の配置換え、湿度管理など、日常生活の中でもきしみを防ぐ工夫は可能です。
「気づいたらすぐに対処」が、家を長持ちさせる最大の秘訣です。
フローリングや床をリフォームするならグランディル
今回この記事では、二階の床がきしむ原因と修理方法についてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけにリフォームすることを検討している方がいらっしゃるかと思います。
フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。
グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。
大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。
また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。
大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。
ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。